検索順位の決まり方の要素の一覧|これを押さえればどんなキーワードも上位化できる。
今日の記事では、
検索順位の決まり方の要素
を私なりに解説したいと思います。
検索順位は、グーグルが認めているところによると、
200の指標を用いて検索順位を決定しているという事です。
※「検索順位は何によって決まり、どうしたら上位化できるのか」
ただ、その200が平等に指標として反映されているか、というと、
確実に優先順位がありそうです。
また、グーグルにしか見れない指標(競合サイトの正確なリンク数など)もあり、
検索順はこれによって決まる!と言い切れるものではないのですが、
個人的な検索順位の決定要素の優先順位を書いていきます。
なお、この検索順位の決定要素に内部的なものを多くは含めていません。
内部要素はかなりサイトの規模に影響を受けます。
今回念頭に置いているのは、大規模なWEBサービスサイトではなく、
小規模~中規模のサイトに対しての要素となります。
自分の体感、体験と、SEOmozの2011年と2013年のranking factorのページを参考にして、
書いていきたいと思います。
外部リンク、参照記事1:SEOmoz2011年検索エンジンの決定要素
外部リンク、参照記事2:SEOmoz2013年検索エンジンの決定要素
当サイトのフェイスブックページです。よろしければ、いいね!お願いします。
『検索順位の決まり方の要素』
要素1:バックリンク (被リンク)
◆リンクの多様性が重視されている
リンクの多様性の内容としては、アンカーテキストの完全一致/部分一致、
リンク元のサイト形式、リンク元のIPアドレスなど。
◆リンクの過剰な設置や一致はマイナス要素である
リンクのアンカーテキストが全て同じである、リンクされたサイトが
全て同じデザインであるなどは、マイナスの働きをする。
またブログフッターなどからの大量リンクはペナルティーになる可能性がある。
◆社会的に信頼性の高いサイトからのリンクを重視
オーソリティーサイトからのリンクを尊重する傾向。
(要素3のドメインも参照ください)
ページランクなどの活用で判断がある程度できる。
要素2:サイト内の文章
◆タイトル、メタ、内部文章にキーワードや類義語、共起語などを入れることは、以前有用である。
◆記事内のタイトル、メタ、文章はそれぞれオリジナルを用いるのがベスト。
軽度の重複はペナルティー要素ではないが、順位下降の主要因となりえる。
他サイトからのコンテンツのパクリは、ペナルティーの誘発、インデックス削除の原因・遠因になる。
◆hタグは、h1へのキーワード挿入による相関関係が認められるが、h2からは相関関係は低くくなる。
◆著者情報をサイト内部に入れることによる上位化は関係性が認められない。
◆自サイトに対するリンクが自サイトの上位化キーワードの大きな要素になっている(※個人感想)
◆地域ごとに同じサービスを提供する様なサイト※も、オリジナルコンテンツを数行でも入れる。
※飲食の宅配や、買取系、修理系、引っ越し、業種など。
要素3:ドメイン
◆完全一致、部分一致ドメイン(EMDドメイン、日本なら日本語ドメイン)は、
影響が弱まったものの、依然上位化の相関関係がある。
◆ドメインが長い場合、マイナスの要素となる。
◆エイジングフィルターなどドメイン年齢は検索に対する影響が弱くなっている(バックリンク除く※個人感想)
◆サイトのオーソリティーを決定する要素として、政府機関.govや
地方自治体.lgや教育機関.edu、団体.or.jpなどのドメインからのリンクを活用している(※個人感想)
要素4:ソーシャル
◆ソーシャルで言及が多いほど、上位化との相関関係がある。
◆はてブは外部リンクとしても依然有効(※個人感想)
要素5:更新頻度
◆更新頻度が高いほど、検索エンジンのクローラーの来訪が増え
検索結果に反映しやすい。(※個人感想)
◆検索エンジンのクローラーは、内部リンクをたどり巡回するので、
内部リンクを最適化する必要性がある。(※個人感想)
◆検索エンジンのクローラーからのアクセスが増えすぎると、
サーバーへの高負荷となる場合があり、サイトの表示速度低下を招き、
検索順位が低下するので、制御する必要性がある。(※個人感想)
上記が私が思う、優先順位の高い検索結果の決まり方の要素です。
なお、個人の体感も入っているので、これだけが要素ではないと思いますが、
この要素をしっかり押さえることで、おおよそのキーワードでの検索上位化は可能だと思います。
◆本日のまとめ◆
検索順位の決定要素を押さえたサイトは、
更新頻度が高く、内部リンクが張り巡らされ、ソーシャルでの言及が多く(内容が濃い)、
社会的権威のある教育機関や団体や政府や地方自治体からのリンクを獲得していているサイト。
という事になる。
『この記事に関連のある記事一覧』
公開日:
:
最終更新日:2013/08/28
検索エンジンを使った集客法など, 検索エンジンマーケティング研究, SEOアドバイザーズBLOG, SEOアドバイザーズ全記事 サイト内の文章 検索順位の決まり方の要素, 検索エンジンに対しての更新頻度, 検索エンジンへのドメインの影響, 検索順位のバックリンク(被リンク)の影響, 検索順位の決まり方, 検索順位の決まり方の要素の一覧, 検索順位の要素
関連記事
-

-
サイトの最適化の対象は「検索エンジン」から「社会」自体に対して、になりつつある件
このサイト(SEOアドバイザーズ.com)では 検索エンジンに対してサイトを最適化する、SEOをテ
-
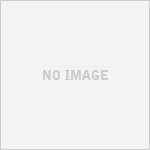
-
2011年6%が13年25%に。スマートフォン普及のデータがグーグルから発表されています。
2011年6%が13年25%に、4倍以上に増えていますが、 韓国は70%以上がスマートフォンという
-
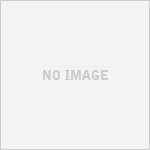
-
過去の失敗SEO|ペンギンアルゴリズムでスパム判定を食らった日。
関連記事:なぜ、SEO対策の失敗例を掲載するのか? 多くのSEOの対策を行う業者が悲鳴を上
-
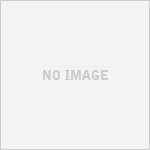
-
ネットの弊害を考える。ビジネス、商売のネタを調べる事。情報の価値について。
ネットの弊害を考えていきます。 まず、今日は、ネットで情報を取得しやすくなった、 という利点の裏
-

-
顧客満足最大化のために、サイト作成時に私が行う18項目のフロー。
ネットが当たり前になった昨今、 「ホームページを作ります」 というビジネスには、なんの付加価値も
-

-
教えたくない、と思うほど役に立つ文章技術「ギャップ法」|コンテンツSEO(マーケティング)ノウハウ
私は、コンテンツSEOを行うに当たり、 文章を書く技術は非常に大事であると考えています。 な
-

-
SNSとSEO|SNS運用における実際の2大パターン
フェイスブックやツイッターなどのSNS。 WEBをビジネスで活用する上でSNSは重要だと多くの方が
-
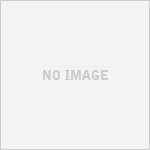
-
ユーザー層に見る、グーグルとヤフーの違い
この記事のデータは若干古いデータを含んでいます。 まず、2011年、宣伝会議のアドタイさんの記
-
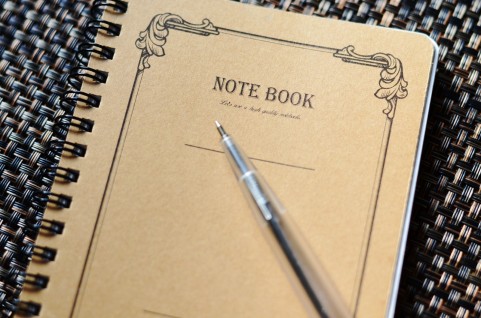
-
グーグルページランク更新停止中。ページランクがなくなって困る事の個人的なまとめ
ブログの更新がだいぶ止まってしました。 ここ1-2月、アルゴリズムの変化かかと思われる変動が、当方
-
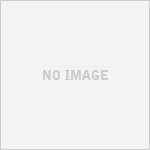
-
google検索エンジンを導入したYahoo! japan
2010年の7月にヤフーは検索エンジンとして、グーグル検索を採用することを発表しました。 2013











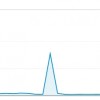



Comment
[...] http://seo-advisers.com/?p=790 [...]